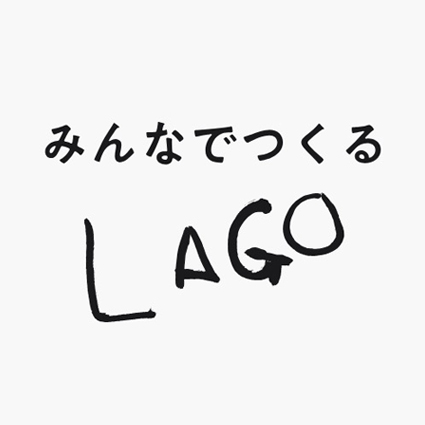2025.09.26 Text : 山﨑 恵理子(LAGO琵琶湖の森)
LAGO生き物だよりvol.3
- # 水と森
LAGO 大津の「琵琶湖の森」では、6月中旬ごろから小さなバッタの赤ちゃんたちが草むらをぴょんぴょん跳び始めていました。
月日が流れ、赤ちゃんたちは立派な大人(成虫)へと成長してきました。今回は琵琶湖の森に棲む、個性豊かなバッタの仲間たちを紹介します。

ショウリョウバッタのメスです。
長い後ろ脚は綺麗に折りたたまれていて、スタイリッシュないでたちがかっこいいですね。体が大きく立派ですが、草食性で主にイネ科の植物(ススキやエノコログサなど)の細長い葉を好んで食べます。

後翅※(こうし)を広げてみました。こんなに美しい翅(はね)をもっているのですね。
危険を感じると、この翅を使って遠くまで飛んで逃げることもあります。
※後翅:二対の翅のうち、後方に位置する一対の翅


ショウリョウバッタには、さまざまな色違いの個体がいます。緑の個体は草むらに馴染み、茶色の個体は地面の色に溶け込み、天敵に見つかりにくくしています。

続いては、涙の痕(あと)のような模様がトレードマークのツチイナゴです。後ろ脚で地面を蹴る力がとても強く、捕まえてみるとトゲトゲした脚で力強く押し返されます。触れ合うたびにとても生命力を感じます。

こちらはツチイナゴの食草の1つ、クズです。ツチイナゴも草食性ではありますが、イネ科の植物を好むショウリョウバッタとは違い、マメ科のクズなど葉っぱの広い植物を好んで食べます。繁茂しやすいクズですが、琵琶湖の森ではツチイナゴを含むいろいろな昆虫の食べ物として管理しています。

赤い口が特徴的なクビキリギスです。漢字で書くと「首切螽斯」と表されるこの虫は、嚙む力がとても強く、噛まれた際に無理に引きはがそうとするとその首がもげてしまうほどだそうで、それが名前の由来となっています。口の周りが赤く、血を吸ったような跡に見えることから「血吸いバッタ」と呼ばれることもあります。琵琶湖の森に遊びに来られたお子様連れのお客様にもご紹介させていただくと、ご家族で楽しんでくださり「クビキリギス、おうちでも調べてみようか」と興味をもっていただけたようでした。小さな体でも、人を驚かせるほどの迫力をもつというのはすごいですね。

草刈りをしていると最近よく出会うエンマコオロギです。名前の由来は、顔にある眉模様が“閻魔大王”を連想させることからきています。一見怖そうな見た目ですが、体は柔らかく眼も大きくて、よく見ると愛嬌のある顔立ちをしています。また、オスがメスに求愛する際に「コロコロコロ…」と鳴く声も美しく、草むらのあちこちから聞こえるその声に、季節が少し秋めいてきたなと癒されます。

エンマコオロギはこういった枯草の下が好きで、刈り取った草を積んだ中からも鳴き声が聞こえてくることがあります。人が草刈りをした後の環境を好んで暮らしていると知ると、琵琶湖の森で私たちと共生してくれているように感じてなんだかうれしくなります。

琵琶湖の森の草むらに一歩足を踏み入れると、こういったたくさんのバッタの仲間たちが飛び出してきてその度に「限られた範囲の草地でも、これだけのバッタが棲み処として利用しているのだな」と実感します。
一度に全てのエリアの草を刈ってしまうとバッタたちの行き場がなくなるため、琵琶湖の森では上の写真のようにエリアを分け、それぞれペースを調整しながら草刈りをしています。そうすることで、ある範囲の草を刈ってしまっても別の範囲には草地が残っていて、そこがバッタたちの新しい棲み処となる、という訳です。これならバッタたちも安心ですね。
草地の環境は近年少なくなっていますが、バッタをはじめ生き物にとってなくてはならない貴重な環境の一つです。 みなさんもぜひ、個性豊かなバッタたちに会いに、琵琶湖の森に遊びにいらしてくださいね。

.jpg)